
労務管理
企業の適正な労務環境の整備を支援し、労働トラブルを未然に防ぎます。労働契約の適正化やハラスメント対策、就業規則の整備など、法的視点から企業の健全な運営をサポートします。
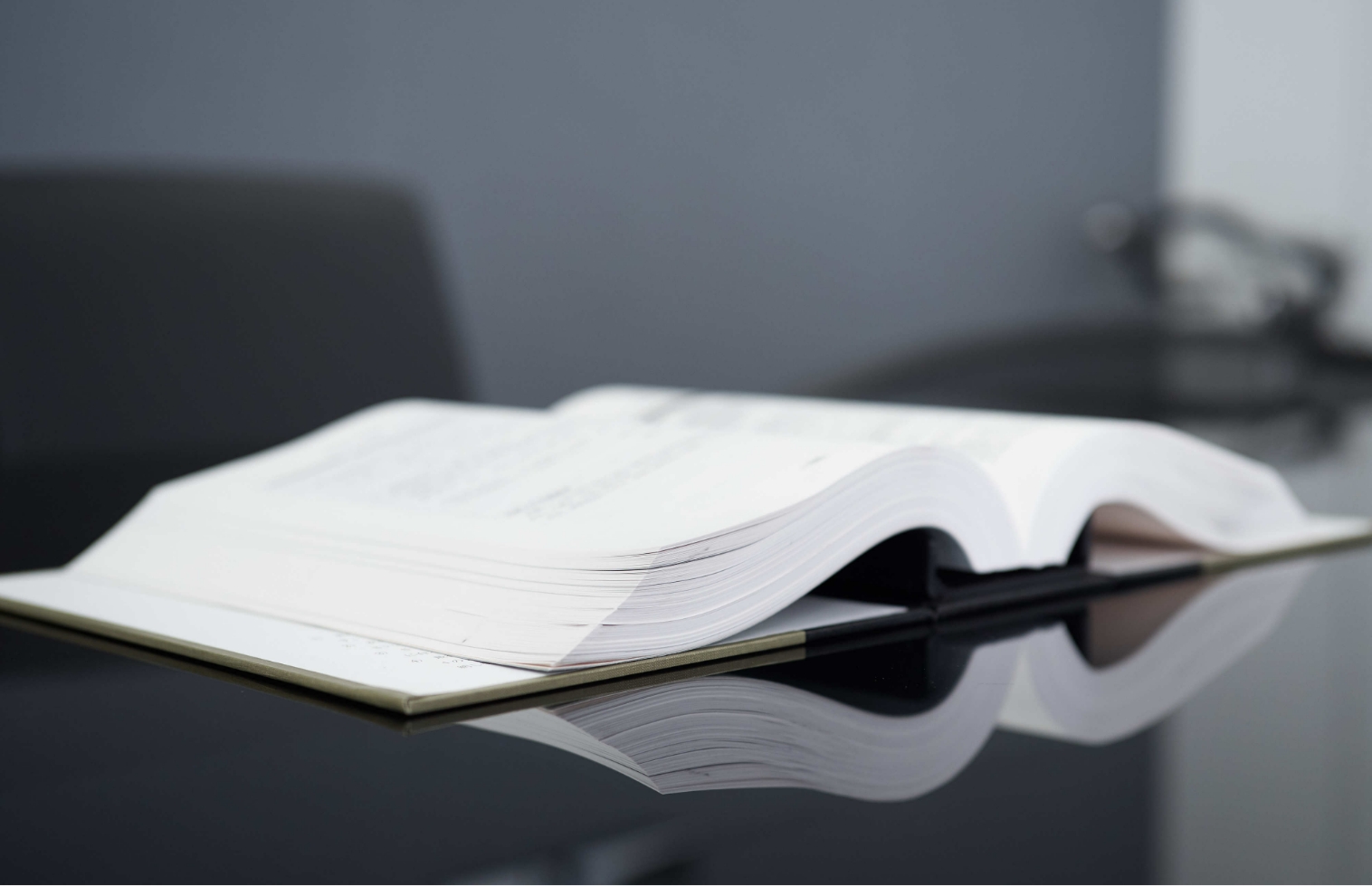
[ 労務管理でよくいただくご相談 ]
- 「新しい法制度を踏まえて規則・規程の見直しを行いたい」
- 「労働者から残業代請求を受けたため、正しい計算方法を確認したい」
- 「労働者の解雇を考えているが、トラブルにならないように進めたい」
- 「社内で起きた労災事故をめぐる諸問題にどう対応したらよいかわからない」
- 「社内で起きたハラスメント事案にどう対処したらよいかわからない」
各種労働問題を経験豊富な弁護士がサポートします
-
就業規則等の作成・見直し
近年、労働関係法規の改正等により、様々な新制度が始まっています。
就業規則や各種規程は、これらの法改正等による新制度を踏まえて、時代に適した内容にアップデートしていく必要があります。
古くからの就業規則等をそのまま備え置いて運用している場合、労働者との間で具体的なトラブルが発生した際に、規定内容がその時点の法制度に適合しておらず、有利な根拠とすることができないといった事態も生じかねません。
このような点に不安がおありの企業様は、是非一度当事務所にご相談いただければ幸いです。 -
賃金に関する諸問題
労務管理上の賃金に関する諸問題としては、以下のような点が挙げられます。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。-
従業員からの未払賃金請求
労働時間の適正な管理や、正しい割増賃金の支給等を行っていない場合、従業員から未払残業代等の請求を受けてしまうことがあります。
2020年の法改正により賃金請求権の消滅時効期間が従前の2年よりも拡大されたことから、実際に支給額に不足がある場合、何年分も遡って支払わなければならないという事態も想定されます。また、未払賃金事件については、付加金という特殊な法制度があり、訴訟上の係争となった場合は、実際の未払賃金額に加えて相当額の付加金の支払いを命じられてしまうという顛末もあり得ます。
このような事態は、企業にとっては大きな痛手となりますので、そもそも従業員から未払賃金請求を受けることがないよう、日頃からただしい賃金額の支給を行うことが肝要です。
また、いざ未払賃金請求を受けたという場合も、必ずしも従業員の主張する額が正しいとは限りませんので、実際に支払義務を負うべき額を慎重に検討する必要があります。 -
実労働時間の管理
未払賃金額の算定にあたっては、基礎となる実際の労働時間を特定する必要があります。
実際の労働時間が長ければ長いほど未払賃金額が高くなる可能性があるわけですが、この「労働時間」は、裁判実務上、労働者が使用者(雇用主)の指揮命令下に置かれている時間をいうと解されており、反対に「休憩時間」は物理的・心理的拘束から完全に解放されて自由な状態をいうと解されています。未払賃金請求事件においては、このような実務上の解釈への当てはめを巡り、実労働時間の捉え方について、会社と労働者とで主張が対立することが少なくありません。このため、会社としては、不相当に長く労働時間を主張されてしまうことがないよう、日頃から労働時間概念についての正しい理解を前提とした管理を行っておく必要があります。
また、いざ未払賃金請求を受けてしまった場合は、会社が主張する労働時間が正しいということを立証しなければなりませんので、証拠となる記録をしっかり保全しておくことも重要です。
-
-
解雇等の処分に関する諸問題
解雇等の処分に関する諸問題としては、以下のような点が挙げられます。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。-
解雇の適法性・有効性の判断基準
解雇が適法・有効といえるためには、一般的に、①法定の解雇禁止の場合に該当しないこと、②客観的合理的理由があること、③社会的相当性があること、④適正な手続を経ていることが必要とされており、これらの要件を欠く場合、解雇は違法・無効となります。懲戒解雇や整理解雇といった特殊な解雇の場合は、これらの各点以外にも特別な要件・要素の充足が必要と解されています。
会社が労働者に解雇を通告しようとする場合、上記のような法律上の要件を充足しているかを慎重に検討するとともに、要件の充足に関する立証責任は会社側にあるため、前提となる事実を立証するに足りる証拠を予め保全しておく必要があります。
とりわけ上記②③の要件の充足については、事案ごとに個別具体的な検討を要しますが、この検討には、専門的な知識・経験が不可欠といえますので、解雇通告の可否等についてお悩みの場合は、是非当事務所にご相談いただくことをおすすめします。 -
解雇無効の主張を受けた場合
解雇通告の対象となった従業員から、解雇が違法・無効だという主張を受けてしまった場合、まずは先の要件に照らして解雇が適法・有効だということを立証できそうかを具体的に検討することとなります。その結果、解雇無効の主張を争うという選択をすべき場合もあろうかと思います。
もっとも、解雇係争は、訴訟等に発展した場合、有効・無効の結論が確定するまでに相当の期間を要するとともに、無効の結論が確定した場合、会社は、対象労働者の職場復帰を受け入れるとともに、経過月数分の賃金相当額(バックペイ)を支払わなければなりません。このバックペイは、会社にとっては大きなリスクであることに加え、最終的な結論の如何とは別に、従業員から訴訟を提起されることはそれ自体会社の社会的信用を損ないかねない事態ですので、解雇無効を本格的に争うか否かは慎重に検討すべきです。
検討の結果次第では、上記リスクを回避して早期の金銭解決を図る方が賢明といえる場合もありますので、従業員から解雇無効の主張を受けてしまった場合は、是非当事務所にご相談・ご依頼いただくことをおすすめします。
-
-
労災に関する諸問題
従業員が業務中の事故で負傷してしまったり、業務上の出来事を原因として精神疾患を発症してしまったという場合、会社は労災として対応を行う必要がありますが、労災に関する諸問題としては、以下のような点が挙げられます。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。-
業務に起因して従業員が負傷・死亡してしまった場合
業務中の事故で従業員が負傷又は死亡してしまった場合、事故の発生等の前提事実自体に争いがない限り、会社は、従業員が各種の労災補償給付金の支給を受けられるよう、労災申請手続に必要な協力を行うべきです。
もっとも、会社に民事上の使用者責任や安全配慮義務違反責任が認められる場合は、労災保険金では賄いきれない損害について、従業員から損害賠償請求を受けることがあり得ます。ただし、労災事故が発生した場合に、必ずこれらの民事責任が肯定されるわけではなく、また従業員にも一定の過失があったと認められる場合は、過失相殺の主張を行うことができます。さらに、従業員が主張する損害額が不相当に高額な場合もあり得ます。
これらの各点の検討には、専門的な知識・経験が不可欠といえますので、労災事故への対応についてお悩みの場合は、是非当事務所にご相談・ご依頼いただくことをおすすめします。 -
業務に起因して従業員が精神疾患を発症してしまった場合
上記のような事故による負傷等以外にも、従業員が業務上の出来事(例えば過重労働や職場でのハラスメント等)により精神疾患を発症したとして労災認定がなされる場合があります。
このような場合も、事故による負傷事案の場合と同様、会社に民事上の使用者責任や安全配慮義務違反責任があるとして、労災保険金では賄いきれない損害について、従業員から損害賠償請求を受けることがあり得ます。もっとも、とりわけハラスメント事案の場合は、事故による負傷事案の場合と異なり、前提となるハラスメントの存否や内容、程度について、従業員の認識と会社側の認識とが相違することが少なくありません。
ただし、上記のような責任追及を受けること自体、会社の社会的信用を害しかねない事態であるとともに、そもそも過重労働やハラスメントを許容しない職場環境の構築こそが会社の使命ですので、日頃からこれらの問題が生じないよう、適正な労働時間管理や必要な研修を実施することが肝要といえます。
-

経験豊富な弁護士がサポートします

-
各種労働問題への幅広い対応と豊富な知識・経験
当事務所の所属弁護士は、様々な労働問題に対応してきた実績があり、豊富な知識・経験を有しています。安心してご相談ください。
-
交渉や手続はすべて弁護士が行います
労働者との交渉や訴訟その他の手続はすべて弁護士が引き受けます。対象労働者と直接話をする必要はなく、裁判所に何度も足を運んでいただく必要もありません。
-
予防法務にも精力的に対応しています
当事務所では、実際に生じた労務トラブルへの対応だけでなく、トラブル回避のための事前の対策など予防法務にも精力的に対応しています。

